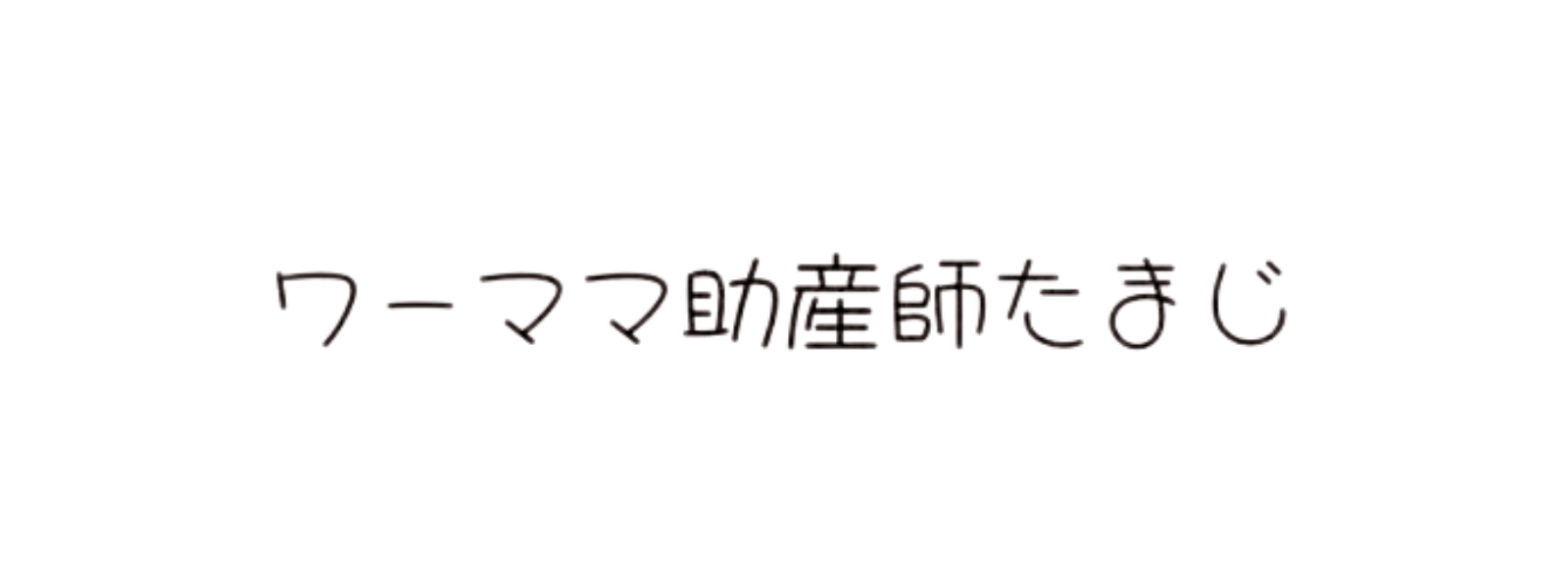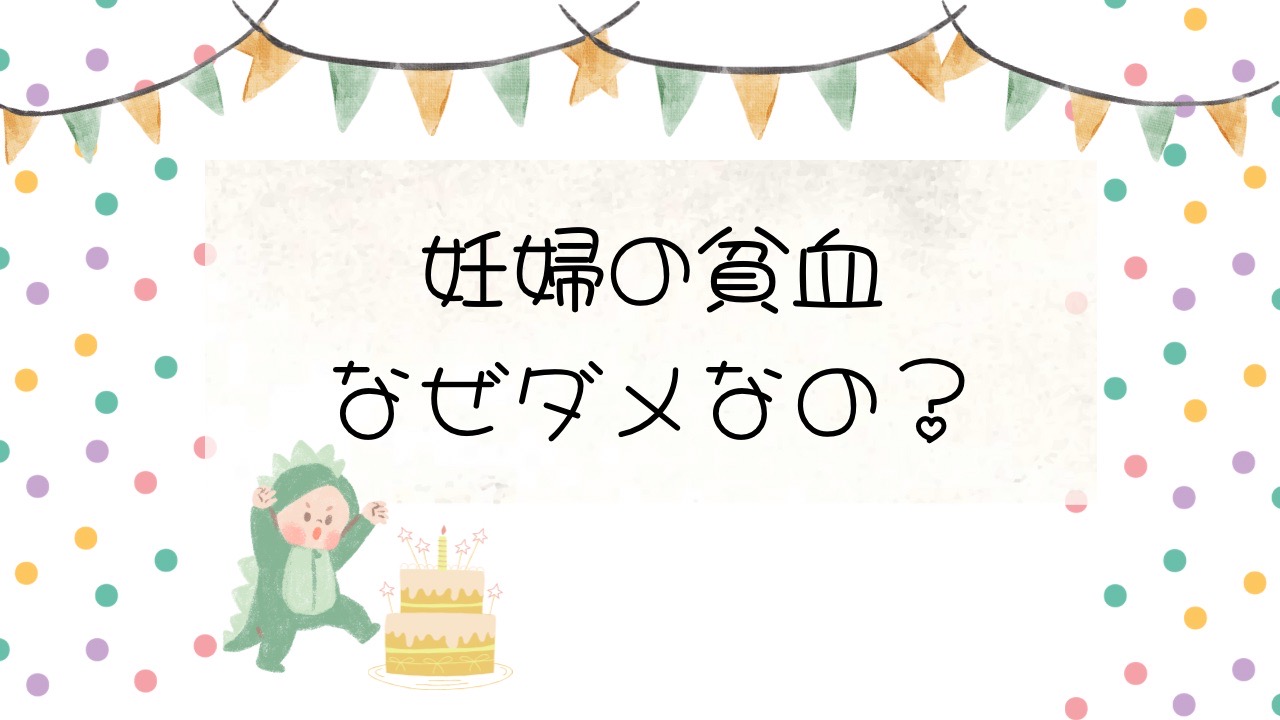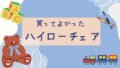妊娠中に貧血と言われてお薬を出されたけど・・・
飲み忘れるんだよねぇ、まあいっか(・∀・)
まってー!
ダメダメダメ!( ゚д゚)
妊娠中に診断される貧血の多くは、鉄分の不足による「鉄欠乏性貧血」です。
なぜ妊娠中に鉄が不足するのか?
貧血になると何が心配なのか?
赤ちゃんへの影響は?
この記事では、妊婦の貧血、その症状、治療方法についてお話ししていきます。

この記事を読み終わったあなたは貧血マスターです!
妊娠中はどうして貧血になりやすいの?

貧血とは、
- Hb(ヘモグロビン):赤血球の成分で、血中の酸素に結合し体内の各組織に酸素を供給する
- Ht(ヘマトクリット):血液中の酸素を運ぶ赤血球の割合
この2つの濃度が低下していることをいいます。
妊婦では以下の場合に、貧血と定義します。
・Hb<11.0 g/dl または
・Ht<33%
妊娠すると赤ちゃんを育てる胎盤に多くの血液が必要となるため、母体の循環血液量が通常時の1.5倍に増加します。
増えた血液量に対し、赤血球も増えますが、それ以上に血漿と呼ばれる血液の水分(細胞以外の成分)が多くなるため、相対的に見て血液が薄くなり貧血を起こします。
また、妊娠中は赤ちゃんの成長のために、お母さんに蓄えられていた鉄分が赤ちゃんに優先的に送られます。
加えて、産後しばらくは悪露と呼ばれる出血があったり、血液から作られる母乳も分泌するので、産後はさらに貧血を招きやすいとされています。

血液が薄くなってサラサラになるってこと?
そうなんです!
妊娠中の薄まったサラサラの血液は、母体にも胎児にとってもよいものです。
サラサラしていることで循環しやすく、胎盤に多くの血液が行きわたります。これによって赤ちゃんは胎盤に集まったお母さんの血液を通して酸素や栄養を受け取ることができます。また、血液が薄くなることは血液の粘性を下げて血栓塞栓症を予防したりもしてくれます。
つまり、
①胎盤に送るために必要な血液量そのものが増える
②母体に蓄えられていた鉄が胎児に優先的に送られる
この2つの理由から、妊婦は貧血になりやすいのです。
貧血の種類

妊娠中の貧血の多くは鉄分が不足する鉄欠乏性貧血ですが、まれに葉酸、またはビタミンB12が不足して起こる葉酸欠乏性貧血もあります。

この2つの貧血を見ていきましょう。
鉄欠乏性貧血
血液は、赤血球・白血球・血小板・血漿で組織されていますが、このうち赤血球の成分であるヘモグロビンは、体内の各組織に酸素を供給するという大切な役割を担っています。
このヘモグロビンを生成するのが「鉄」です。
赤血球中のヘモグロビンは、ヘムという鉄とグロビンというタンパク質が結合してつくられています。ヘモグロビンの赤茶っぽい色は鉄の色で、その大部分が鉄で構成されています。
・ヘム:鉄
・グロビン:タンパク質
鉄が不足するとヘモグロビンの量が減少し、その結果、血液の酸素を運搬する力が落ちてしまいます。
これが「鉄欠乏性貧血」です。
葉酸欠乏性貧血
葉酸欠乏性貧血は、巨赤芽球性貧血とも呼ばれ、葉酸やビタミンB12が不足することによっておこる貧血です。
葉酸やビタミンB12が不足すると、DNAの合成時に異常が生じ、通常より大きなサイズの赤血球の元(巨赤芽球)が作られます。巨赤芽球の多くは赤血球になる前に壊れてしまうので、正常な赤血球が不足し貧血が起こります。
これが「葉酸欠乏性貧血」です。
また、葉酸欠乏性貧血は鉄欠乏性貧血を合併していることが多いのも特徴です。
葉酸は性別、年齢問わず重要な栄養素ですが、妊娠中は特に必要とされています。葉酸欠乏性貧血としての対策はもちろん、葉酸が妊娠中に重要とされているのは神経管閉鎖障害のリスク低減のためです。
「神経管閉鎖障害」とは
妊娠初期である妊娠4週目〜12週目頃に発生する先天異常の一つで、神経管がうまく作られない状態で、二分脊椎や無脳症となります。

そういえば、急に立ち上がった時にフラフラするのも貧血???

それは、「脳貧血」と言って別もの なんです。
妊娠28週ぐらいから急に立ち上がった時に目の前が真っ暗になり、場合によっては倒れてしまうような脳貧血を起こす人がいます。
しかし、ここでの貧血と脳貧血とは別もので、鉄欠乏性貧血とは関係ありません。
脳貧血の自覚がある場合はすぐに立ち上がらないで、頭が一番最後になるように起き上がると対策が出来ます。
貧血が与える影響

それでは、貧血が与える影響について見ていきましょう。
妊娠期
妊婦時にみられる貧血を総称して「妊娠貧血」と呼びます。
先ほどのおさらいですが、貧血とは、血液中の酸素に結合しているヘモグロビンの濃度と、血液中の酸素を運ぶ赤血球の割合であるヘマトクリットが低下していることをいいます。
妊婦では以下の場合に、貧血と定義します。
・Hb<11.0 g/dl または
・Ht<33%
成人女性の貧血の基準はHb<12g/dlですが、妊娠すると生理的に貧血傾向となるため、上記のように貧血基準が若干甘くなります。
それでも、バランスの悪い食生活によって鉄の摂取量が少なくなると、この基準すらクリアすることができず、鉄欠乏性貧血となってしまう妊婦は少なくありません。
妊娠による貧血は一般的に無症状であることが多いですが、場合によって以下のような症状がみられる場合があります。
・息切れ、動悸、倦怠感(特に動作時)
・顔色不良、顔面蒼白
・起立性低血圧、立ちくらみ
・皮膚・爪床の蒼白感
・その他の不定愁訴(朝起きにくい、首や肩がこる、だるい、頭が痛いなど)
赤ちゃんへの影響
妊娠初期〜中期に貧血だった場合、早産や低出生体重児の赤ちゃんが生まれるリスクが1.2倍を超えています。
そして急速に発症した重症貧血妊婦(Hb≦6mg/dl)では、赤ちゃんがおなかの中で亡くなるリスクも高くなります。
おなかにいるときに十分な鉄を蓄えられず、生後半年から1年頃に赤ちゃんが貧血になるケースもあります。
ただ、生後半年から2歳ごろには、赤ちゃんも自分で鉄分を摂らないといけなくなるので、母体が貧血でなくても鉄不足になる危険性もあります。
♯早産、低出生体重児
♯子宮内胎児死亡
♯児の貧血
分娩時・産後
先ほどもお伝えしたように、貧血時の症状は動機・息切れ・倦怠感など体力がない状態です。
したがって出産時に貧血の場合、効果的な陣痛がつかず、微弱陣痛としてお産が長引く可能性があります。さらに陣痛が弱く赤ちゃんを押し出せないため、分娩停止となる可能性もあります。また、遷延分娩(初産で30時間以上、経産婦で15時間以上経っても出産に至らない場合)となった場合に、子宮復古不全といって産後の子宮の収縮が悪くなり、分娩時・産後の出血も多くなる弛緩出血を起こす可能性があるので、場合によっては輸血のリスクも高まってきます。
また、産後も貧血が進み、産後の体力に影響する心配もあります。産後は妊娠中のような長時間睡眠ができなくなり、初めのうちは赤ちゃんのオムツ替えや授乳などで生活リズムが乱れます。
産後は体力勝負です。
また、貧血の女性が産後にうつを発症するリスクは、貧血がない女性と比べて約6割も増えるという研究結果が出ています。貧血になると全身の倦怠感や疲れが取れにくくなり、気力が低下することが要因です。
出産時に、過度な出血や貧血があった場合は、その回復に栄養が利用されてしまい、血液から作られる母乳は十分に出ない可能性もあります。
♯微弱陣痛
♯遷延分娩
♯分娩停止
♯子宮復古不全
♯弛緩出血
♯産後の体力低下
♯産後うつのリスク
♯母乳分泌不全

ヒェ〜
貧血ってこんなにも大変なことになってしまうんだね〜
妊娠中の貧血対策
主な治療は、食事療法や、鉄剤などを用いた薬物療法です。
鉄分や葉酸を多く含む食材を積極的に取るよう指導がなされ、必要に応じて薬の投与を行います。
これらの治療を行っても改善がみられない場合や重度の貧血の場合は、輸血が検討されることもあります。
食事療法
貧血を予防するためにはまず、毎日失われる鉄を食事からしっかり摂ることが必要です。
妊娠中の鉄分は妊娠前の約3.1倍の量が必要になります。
鉄分の種類には、消化吸収されやすい「ヘム鉄」と、消化吸収されにくい「非ヘム鉄」があります。吸収を助けるビタミンCやたんぱく質も一緒に摂るようにしましょう。
ヘム鉄

・動物性食品に含まれている鉄分
・吸収率が25%と高い
レバー(串1本 2mg)、赤身肉、カツオ、あさり、しじみなど
※レバーに含まれるビタミンAは、摂りすぎると胎児の先天異常の発生率が高くなるという報告があります。食べるときは週1~2回、1食あたり60g(2串)程度にしましょう。
非ヘム鉄

・植物性食品に含まれる鉄分
・吸収率が3〜5%と低い
・お茶の成分であるタンニンが吸収を阻害する
・ビタミンCやラクトフェリンで吸収率が高まる
ほうれん草、ひじき、卵黄、プルーン、小松菜(1茎 1mg)、春菊、納豆(1パック 1.5mg)、豆乳、大豆、油揚げなど
葉酸を多く含む食べ物
焼海苔、鶏レバー、わかめなどの海藻類、ブロッコリー、ほうれん草、枝豆、大豆、アスパラガス、モロヘイヤ、いちごなど
食べ物以外から鉄分を摂取する方法
この他食べ物以外から鉄分を摂取する方法として、鉄のフライパンや鉄瓶など、鉄で作られた調理器具を使用すると、鉄が溶け出し鉄分を吸収することができると言われています。
鉄分の吸収を阻害するもの
鉄分が多く含まれている食事とは別に、実は鉄分の吸収を阻害するものもあります。

なぬ!?教えてくれぇ〜
それはコーヒーや紅茶、緑茶などです。
コーヒーや紅茶、緑茶などは鉄分の吸収率を下げると言われています。これはコーヒーなどに含まれる「タンニン」という成分が原因で、タンニンは鉄の吸収を阻害してしまう働きがあります。
特に食事摂取から1時間以内にコーヒーなどを摂取すると、鉄分の吸収が阻害されます。
コップ1杯の適量なら問題はありませんが、食事と一緒にガブガブ飲むのは控えたり、1時間以上時間をあけてから飲むようにしましょう。
薬物療法
内服薬が第一選択となります。
・フェロミア
・フェルム(徐放剤)
・インクレミン(シロップ剤)
・フェロ–グラデュメット(徐放剤)
・リオナ(消化管の副作用の軽減が期待される)
※徐放性製剤・・・薬の成分が少しずつ長時間放出され続けるように加工された製剤
しかし、鉄剤は服用により、悪心、食欲不振、下痢、便秘などの消化器症状が現れることがあります。鉄剤による副作用のため服薬が困難な場合は、注射で投与します。
・フェジン(ブトウ糖液による希釈、2分以上かけて投与)
・フェインジェクト(静注:5分以上かけて投与、点滴静注:生理食塩駅で希釈し6分以上かけて投与、週1回・1~3回の投与で治療が終了する)
・モノヴァー(生理食塩駅で希釈、15分以上かけて投与、週1回・2回の投与で治療が終了する)
これらの点滴を投与したことがある人はお分かりだと思いますが、真っ黒な液体なんです。
・・・これを注射するの!?( ゚д゚)
と、驚く方もいると思います。笑
フェジンを静脈注射するときに注意するポイントは?
フェジンをワンショットで投与する際は、2分以上かけて行う(緩徐に静脈内投与)必要があります。
理由は、ワンショット投与により一過性の頭痛、全身倦怠感、心悸亢進、おしん、蕁麻疹、顔面紅潮などの副作用が認められ、投与速度を緩徐にすることでその副作用が軽減するためです。
モノヴァーはファインジェクトより投与回数が少なくて済む
ほとんどの方が3回投与が必要なフェインジェクトに比べて、モノヴァーは投与回数が1回少なく済みます。
血管外へ漏出したら!?
血管外に漏出した場合には、漏出部位周辺に皮膚の炎症及び長期にわたる色素沈着を起こすことがあるので、注射に際しては血管外に漏出しないよう十分注意しましょう。血管外漏出が認められた場合は、適切な処置を行うようにしてくださいね。
なお、これらの治療を行っても貧血が改善しない場合や、重症度の高い貧血の場合は輸血が必要になることもあります。

鉄剤を内服したら、便の色が黒くてびっくりしたっ!
そうなんです。鉄剤を内服すると便の色が黒くなって、初めはびっくりしますよね。
それは、吸収されなかった鉄が消化管で酸化され、黒色となって便中に排泄されるためです。
さいごに
妊婦の貧血について解説していきました。
妊娠中はどうしても貧血になりやすい時期です。
しかし鉄剤が処方されても効果が出るまでに1〜2ヵ月かかることもあります。そのことを念頭におき、毎日コツコツ忘れずに鉄補給をしていくことが大切です。
女性にとって貧血は当たり前で、あまり心配していない方もいるかもしれません。ですが、妊婦さんはお産が長引いたり、出血が多くなったり、赤ちゃんが貧血になったり、母乳の出が悪くなったりと、悪い事づくしです!
鉄剤の内服処方をされた場合はきちんと内服することはもちろんですが、食生活についても正しい知識をつけて、ぜひ生活に活かしていただきたいです。